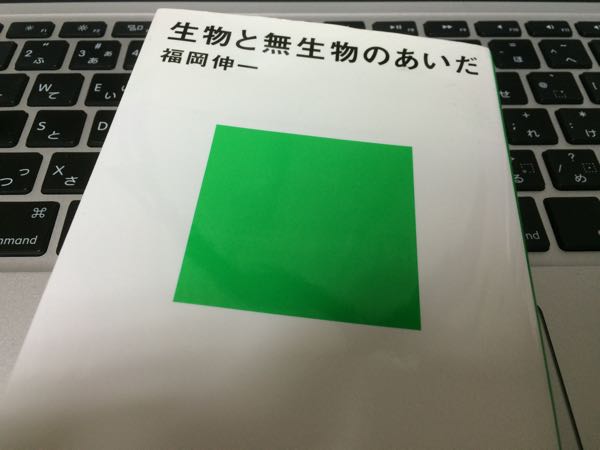
「生物と無生物のあいだ」
この本は、高校時代に後輩が読んでいたのをなんとなく覚えています。
「生物と無生物のあいだ」を読んでみたので、読んだ感想などについて書いてみます。
「生物と無生物のあいだ」の概要
「生物と無生物のあいだ」は全15章からなります。
各章にはそれぞれ題名がついていますが抽象的なので、自分なりに内容をまとめてみました。(同じ章もあります。)
| 章 | 内容 |
|---|---|
| 第1章 | 野口英世のアメリカでの人物像 |
| 第2章 | 遺伝子の本体がDNAだという発見 |
| 第3章 | DNAはACGTの4種類で構成されている |
| 第4章 | PCR(DNA複製方法)の紹介 |
| 第5章 | PCR発見の経緯 |
| 第6章 | 論文審査の問題点 |
| 第7章 | 発見のための心の準備 |
| 第8章 | なぜ原子は小さく人は(原子に対して)相当大きいのか |
| 第9章 | 動的平衡とは何か |
| 第10章 | 動的平衡と相補性 |
| 第11章 | 小胞体について |
| 第12章 | 細胞膜のダイナミズム |
| 第13章 | 膜に形を与えるもの(GP2) |
| 第14章 | ES細胞登場による数・タイミング問題の解決 |
| 第15章 | 生命は機械ではない。時間軸を持っている。 |
全てつながっている話です。
全体としては、「生物とは何か」という問いを考えながら、DNA(遺伝子の正体)の研究に勤しんだ人々の物語が続きます。
おすすめの対象読者
以下の人が読むと楽しいように思いました。
- 研究者
- 理系大学を目指す高校生
- 生物学を勉強した高校生・大学生
- 研究室に入る前の大学生
- 研究室に所属した学生
「生物と無生物のあいだ」を読んだ感想
生物学(DNA)をめぐる物語となっているので、専門用語が頻繁に出てきます。
特に第11章以降は結構難解でした。
ただ、補足の絵がありますのでイメージはしやすかったです。
高校や大学の生物で習った単語が出てきたのでそういった前提知識があると読みやすいです。
ただ、その部分はわからなくても構わないと思います。
研究者としての正しい思考プロセスや陥りがちな穴などが丁寧に記述されていました。
歴史的な発見を一緒に解き明かしていくスタイルで物語は進んでいく所が面白いところ。
筆者がハーバード大学医学部研究員だった事から、一歩踏み込んだ所の話まで書かれていたのが印象的でした。
これはもっと昔に読んでおきたかったなという1冊でした。
ちなみに本書は第29回サントリー学芸賞<社会・風俗部門>(2007)、第1回新書大賞(2008)を受賞しています。
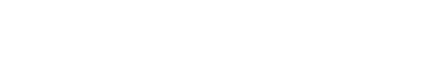
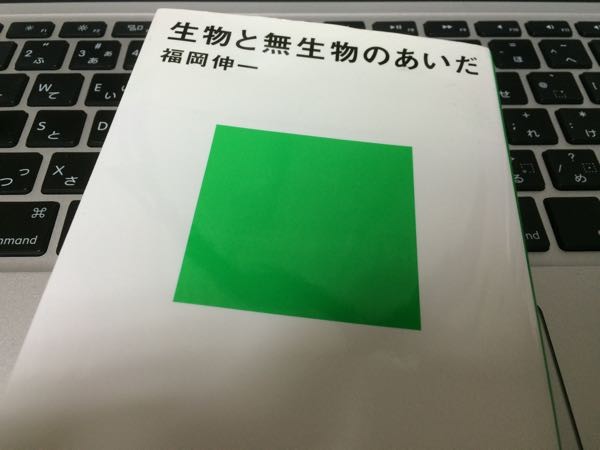


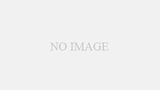
コメント